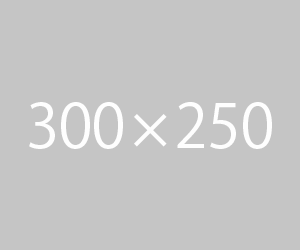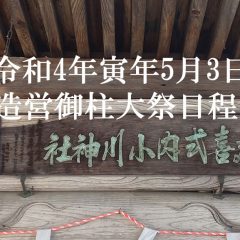小川神社の歴史
口碑に伝う、延喜式神名帳に所載の当社なりと。
社伝旧記明和年中流失す。
更に昭和八年社家火災に遭遇し寛政二年神祇領連載許状を承れる礎に引き継がれてきた記述書類・古文書等を焼失し鎮座伝承不詳なるも、
往古古山に土豪某居住しこの地を開拓し、安曇郡青具峰より発する青具川と本村筏山の麓に発する小祢川と合流する辺の地を下し勧請地名(伝承によれば弘仁五年(814) 継体天皇六代の後裔酒人小川真人当地訪問)により小川神社と称し、延長五年(928) 延喜式神名帳記載、治承・文治(1177~1190)の頃、当地方を上西門院領小川庄とあり、吾妻鑑には小川を小河と表記しあり。後裔古山に城を築き小川を氏とし勢力を得。
累代継承し左衛門貞綱に至り承久の乱戦功により小川庄地頭小川城主として小川郷三千石を領し当社を崇敬し社殿壮麗に修築す。
爾来遠近敬仰する大社にして趨勢を誇るも応仁二年(1468)の兵乱に小川氏敗退し随って社殿疲弊衰頽を極む。
其後(武田氏知行書天文二年(1534) 大日方弾正正忠小五郎長政この地を領するに至り旧観に復す。
慶長三年上杉景勝会津移封に際し大日方氏浪人土着し古山城墟址となり社家数戸も散亡し爾後旧に復せず。
古来の鎮座地は現地隣接丘上宮平にあり観月の名所と謳われたが、大日方氏祈願所の現在地に造営して鎮座し、古来の鎮座地には御射山神社が残り、その後御射山神社地境内地は校舎用地となりて当社に合祀す。
大日方氏尊崇の遺風は末裔当主が敬神講を組織し毎年五月、八月、十の十七日に大日方氏奉幣行事等の月次祭を斎行(元来は御日待神事と称し毎年正月十七日氏子と共に参拝し連夜斉籬す。) 中昔は大宮大明神、諏訪大明神宮と称せしが、寛政二年八月吉田家へ社号宣旨を願い告文を受け小川神社とす。
明治二年正月華頂宮御祈願所として裏菊御紋幕及び提灯等を拝領す。
従来小川村小根山の産土神として明治五年高二石社領之処上知す。明治六年四月村社に列し、大正九年十一月三十日郷社に昇格す。
昭和二十四年神社本庁包括神社。
現在の御本殿の創建は享保十四年(1729)十月の造営。
本殿覆屋・幣殿拝殿は昭和三十一年新築造。
小根山地区の歴史
小根山地区における考古学調査の成果により、小根山地区の歴史は縄文時代中期までさかのぼられている。
数千年前にこの地に人類が居住し、狩猟・採集生活が営まれていた。
史料の上では平安時代の「延喜式」神名帳(古今和歌集と同時に成立) 小川神社が初出であり、ついで天養文書は小川庄に関するものであり、中世武士団の成長がしられる。 鎌倉幕府の末期には小川庄内に小根山郷が成立したとみられる。
明治八年三月小根山村と立屋村が合併し小根山村となり現在の小根山を構成した。明治十年ごろの耕地は、田二十二町六反一畝、畑二一七町四畝、戸数二四二戸、人口男六二五人、女六五〇人、計一二七五人であった。
小根山は自給自足経済をいとなむ村落共同体であり、住民の生産と生活はすべてこの村を基盤として展開された。
なかでも共同体としての連帯感は産土の「明神様」(小川神社)と「御射山様」に統一された。自給自足経済から商品生産を展開させて村人は経済的剰余を確保し、共同体の枠をこえて交流し情報を収集しながら視野を拡大、生活を向上させた。
いわゆるそれは麻の栽培と家内手工業により加工し商品化された。小根山村は交通の要所であり小根山村を通り善光寺町・大町へ通ずる街道は「麻の道」であり、麻取引の拡大とともに、馬の飼育も盛んになった。
麻は小根山の特産であった。いわば麻は麻年貢として金納がみとめられていた。日影には寛永年口留番所がおかれ松代藩内からの麻の移出をきびしく取り締った。
小根山村の小川神社
三河生まれの著名な旅行家、当時の庶民の生活などを書き残した民俗研究家菅江真澄が、 天明四年(一七八四) 新町村に泊まっているときに、塩入氏に聞いた話として小川神社の事をかきとめている。
十八日あるじひとひ、ふつかはここにありねと、ひたぶるにとどめぬれば、同じ宿におるに、上条村にすめるといふ、かのしおいり氏といふ人ぶらり来たりて、小川神社は小根山村におましあるかみとかたりけるを聞いて、 をね山の木々のした露ちりつもりながれ、 小河の神やますらん、
たったこれだけの記述ではあるが、当時この地方でも、小根山の小川神社はかなり有名なお宮で、菅江によって注目されている。